――「良い人」の定義の罠と、同調圧力の正体
序章:「良い人」とは誰のための“良さ”か
あなたは「良い人でいなさい」と言われたことがあるだろうか?
多くの人は、それを「人に迷惑をかけず、空気を読み、反抗しないこと」と理解している。
しかしそれは本当に「善」なのか? それとも“都合のいい人間”を作るための定義なのか?
善と徳の違い──本質を見失わせる仕組み
- 善とは、道徳的・倫理的に「良い」とされる行為
- 徳とは、内面的に備わった人格・品格・知恵の総体
現代社会は「善」のふりをした「徳なき行為」に満ちている。
たとえば:
- 自分の利益のために募金する
- 目上の人にだけ礼儀正しく振る舞う
- 外面だけ丁寧にして内心は傲慢である
これらは“演出された善”であり、真の徳とはかけ離れている。
「良い人」は誰の定義か?
- 会社に逆らわない
- 学校で目立たない
- 親の期待通りに生きる
これらはすべて、「組織や集団にとって都合の良い存在」でしかない。
社会は「従順さ」と「無害さ」を“善”として評価するが、
そこに自己決定も、信念も、哲学も存在しない。
同調圧力という“美徳の暴力”
日本社会では、「和を乱さないこと」が美徳とされている。
しかしこれは、思考の多様性を押し殺すための圧力でもある。
- 空気を読め
- 皆と同じであれ
- 浮くな、出るな、黙れ
こうした言葉は、「善い人間」であることを盾にして、
他者を黙らせる装置として機能する。
真の徳とは何か?
真の徳は、以下のような要素から成る。
- 正しさではなく本質を見抜く知性
- 他者に迎合せずとも誠実であり続ける強さ
- 時には“反逆”することで守る本当の倫理
- 自分の意思で行動し続ける勇気
つまり、善行とは“内なる徳”が自然と表出したものであって、
評価されるための「ふり」ではない。
結び:評価されるために善を演じるな
社会にとっての「良い人」になることは簡単だ。
しかし、それは自分の魂に背く人生でもある。
本当の善とは、誰に評価されなくても、
誰にも認められなくても、
信念と知性に裏打ちされた行動である。
次回は、さらにこの“支配の定義づけ”がどうやって国家レベルで機能しているのかを掘り下げていく。


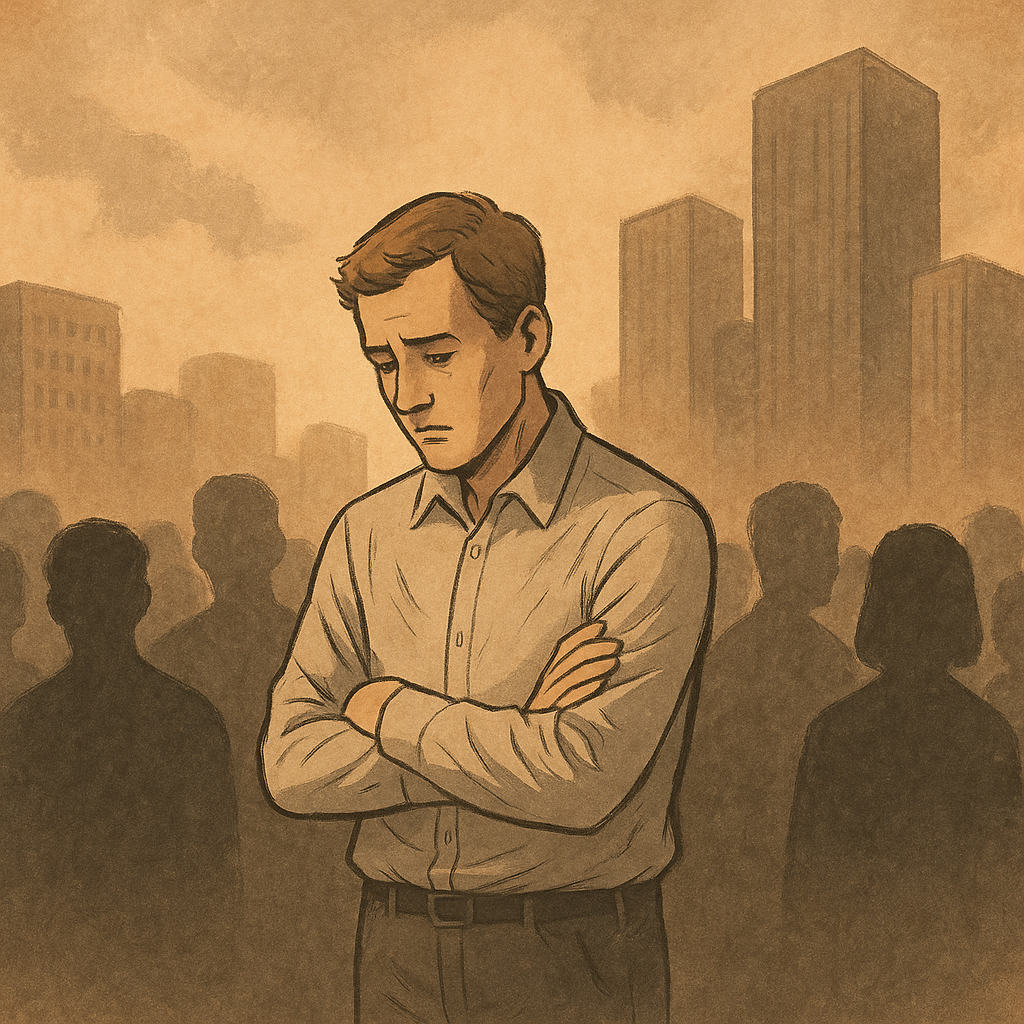
コメント