序章:「選んでいるようで、選ばされている」
私たちは日々、膨大な情報の中で「自分で選んでいる」と思っている。
ニュース、テレビ、SNS、YouTube、ネット記事…。
だが本当に、自分の意思で選んでいると言えるだろうか?
マスメディアの基本構造:支配の道具としての役割
テレビや新聞は、中立的な報道機関ではない。
背後には広告主・政府・スポンサーという“支配する側”の意図がある。
- ある事実は強調され、ある事実は黙殺される
- スタジオの演出、BGM、ゲスト選定までもが操作されている
- 「国民の声」として流れる街頭インタビューすら編集された“意図”である
SNSは「自由な発信ツール」ではない
SNSは民主的な言論空間のように見える。
しかし、そのアルゴリズムが人々の“視界”を操作している。
- バズる投稿は共感を誘うが、真実とは限らない
- 感情的な言葉が拡散され、冷静な考察は埋もれる
- 自分が見たいものしか見えない「フィルターバブル」
- 炎上、誘導、分断──これらはすべてプラットフォームに利益をもたらす構造
「選択肢」は誰かが設計したもの
テレビもSNSも、情報の流れそのものが“選ばされる思考”を形成している。
私たちは「多数派の意見」「いいねの多い意見」に安心し、無意識に従ってしまう。
- 思考を停止して流されることが習慣化されている
- マジョリティの安心感が思考を麻痺させる
- 結果として、「自分で考えていない」人間が量産される
操作に気づくにはどうすればいいか?
まずは「自分が受け取っている情報の出所」を常に意識することだ。
そして「反対意見」「不都合な事実」にも目を向ける訓練をすること。
- 情報源を複数照合する
- 数字・統計・一次情報を自ら読み解く
- 感情を煽られたときこそ立ち止まる
- フィルターの外に出る努力をする
終わりに:情報は支配のためにある
情報は「自由のための道具」でもあり「支配のための道具」でもある。
どちらに使われるかは、受け取る側が“気づいているかどうか”にかかっている。
このシリーズを通して、
私たちは「当たり前」を疑い、「情報に支配されない思考」を取り戻していく。
思考することは、最も根源的な“抵抗”である。

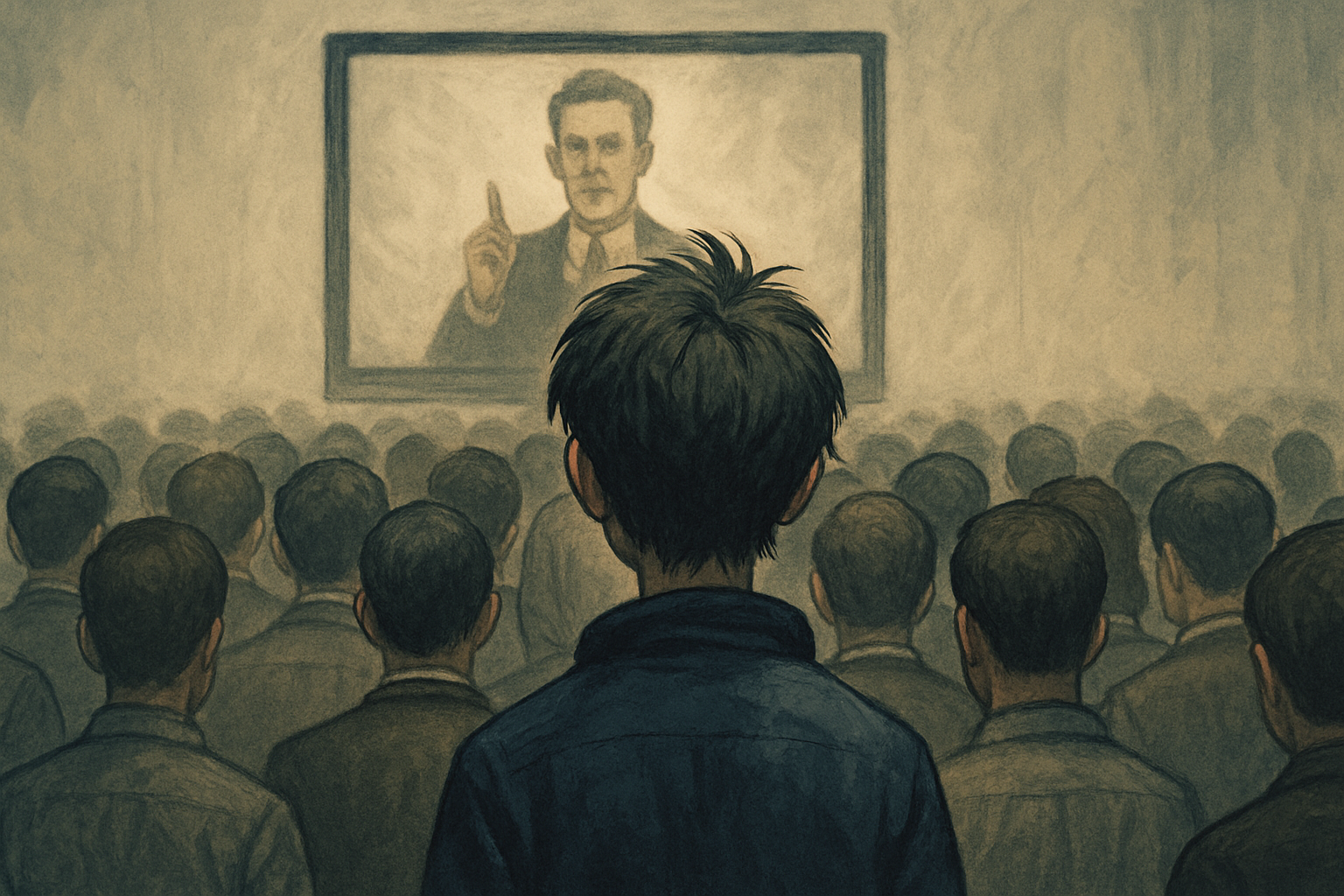

コメント