SNSは自由を与えたのか、奪ったのか
SNSが登場したとき、人々はこう信じた。
「発信できる時代が来た」
「自分の声が届く世界になった」
「誰もが自由に意見を言える社会になった」と。
だが、現実はどうだろう。
自分の言葉は、炎上や批判のリスクを常に伴い、
言いたいことを“言えない”空気が蔓延している。
それは自由ではない。
それは、“牢獄”である。
“いいね”と“RT”が作り出す監視の網
SNSの設計は非常に巧妙だ。
- 「共感されること」が評価の基準
- 「ウケること」が可視化される
- 「異質な意見」が叩かれる構造
つまり、他人の目を気にし、空気を読む者が生き残る世界。
それは、かつての村社会と何一つ変わらない。
いや、それ以上に恐ろしいのは、
“数の暴力”がリアルタイムに可視化されるという点にある。
・数字が示す“沈黙の圧力”
・少数派=間違っているという誤認
・アルゴリズムによる選別と囲い込み
SNSは自由の場ではなく、“従順さの競争”の場となった。
SNSの自由は“同調圧力”と引き換えに成立している
たしかにSNSは自由だ。誰でも何かを書ける。
だがその自由には、“代償”がある。
- 発言すれば、叩かれる可能性
- 空気を読まなければ、孤立する危険性
- 批判を恐れて、自己検閲が始まる
これは自由ではない。
これは“見えない檻”の中で振る舞う訓練された囚人の姿である。
SNSの設計者は誰か──支配の構造を見よ
問題は、個人の使い方ではない。
構造そのものが「従わせるため」に設計されているという点だ。
- アルゴリズムで“見せたい情報”だけを流す
- 過激なコンテンツが拡散しやすい設計
- 炎上構造で注目を集め、広告収益を最大化
つまり、SNSとは
「大衆の感情」と「発言の傾向」を管理する感情工学の装置である。
支配は、明確な命令ではなく、“設計された環境”で実現する。
結論:本当の自由は、他人の目を捨てた先にある
SNSにおいて、自由は演出されているにすぎない。
その実態は、同調と沈黙による管理であり、
意見の表明ではなく、“空気の読解”が要求される社会だ。
- 本当に言いたいことが言えているか?
- 「いいね」の数に支配されていないか?
- 誰かの視線を恐れて、言葉を飲み込んでいないか?
自由は、自分の中にしかない。
それは、SNSの構造に気づくことから始まる。


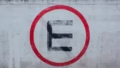
コメント